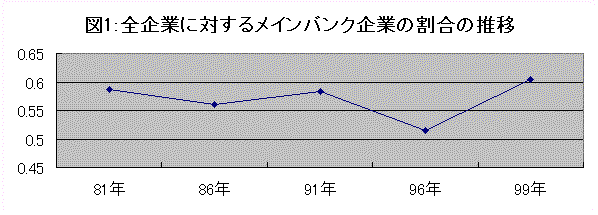
90年代のバブルの崩壊以降、日本の高度成長期を支えてきた様々な日本型システムの限界や問題点について指摘されるようになり、そういったシステムの崩壊が実際に起きてきた。日本長期信用銀行の破綻に代表される、大蔵省の「護送船団」方式の金融行政の崩壊などは、その最たる例である。このような動きは、日本の金融システムの大きな特徴であったメインバンク制度についてもその例外ではないといわれる。資本の効率、株主の利益といった指標が重要視されるようになり、また、時価主義会計への移行を控えての企業と銀行間の株式持ち合いの見直しといった動きなどがその一つの例であろう。しかし、そのような認識が広まっているにもかかわらず、このことについて実証分析を行っている文献が、私の知る限りではほとんど見あたらない(*1)。そこで、この論文では、日本企業の高成長を支えてきたといわれるメインバンク制度について、その機能の変化を分析することにした。 通常、メインバンク関係は、企業と銀行との間の以下のような関係のうち複数がみたされている場合に、成立しているとされる。(*2)
(1)当該銀行から長期継続的に他のどの銀行よりも多額の資金融資を受けていること
(2)当該銀行が重要な株主であること
(3)企業に銀行から役員が派遣されているなどの人的関係があること
(4)融資以外の各種金融取引においても主力の取引関係にあること
(1)長期継続的な取引によって企業についての情報生産が効率化される。また、様々な金融取引を通じて(取引口座の管理等)、企業の正確な状況を把握することが可能になる。このような、情報生産の効率化、情報の質の高さを通じて、メインバンク関係は金融取引に付随する情報の非対称性の問題を緩和する。結果として、企業に対してより多くの資金をより低いコストで提供することが出きるようになる。(投資資金の効率的供給機能)
(2)企業経営のモニタリングを、(1)のように情報の面で優位性を持つメインバンクが投資家を代表して行うことによって、企業経営の効率性が維持される。(企業経営のモニタリング機能)
(3)企業が経営危機に陥った場合、再建可能であると判断されれば、メインバンクが経営に介入し、当該企業の救済活動を行うことがある。また再建が不可能な場合でも、より低いコストでの清算が可能である。(企業経営に対する保険提供機能)
以下の構成は次のようである。まず、第2節では、分析の基礎となる理論についてまとめ、先行研究について簡単に紹介する。第3節では、分析の枠組みを説明する。第4節では、第3節の枠組みによって、メインバンクの機能について分析する。第5節では、今回の分析結果からの含意をまとめている。
通常、企業が設備投資を行おうとする場合、二通りの方法が考えられる。内部資金によって投資を行う方法と、外部から資金を導入することによって投資を行う方法の二通りである。しかし、この二つの方法のコストは同一ではない。
外部資金を導入して投資を行う場合には、企業の経営者と、外部の投資家との間で情報の非対称性が生じる。このような、情報の非対称性が生じる理由としては、
①一般の投資家は、経営者や既存の株主の直面している投資機会について正確な情報を入手し得ないこと、
②一般投資家は、分散投資によって個別企業に特有のリスクを回避することが可能であるため、個々の企業に対する利害関係がモニタリングの費用と比べて小さく、モニタリングを怠り勝ちであること、
しかし、メインバンクを持つ企業の場合には、上述のように、メインバンクのモニタリングによって、情報の非対称性の問題が緩和される。そのため、エージェンシーコストも引き下げられ、結果として、外部資金(この場合は銀行借入)のコストが、メインバンクを持たない場合に比べて、引き下げられると考えることができる。このことは、メインバンクを持つ企業は、投資額の決定に対する内部資金の制約が相対的に弱められるということを示唆していると考えられる。 このような視点から、メインバンク関係の投資に対する影響を分析した論文に、Hoshi,Kashyap and Scharfstein(1991)がある。ここでは、日本企業を、企業系列グループに属している企業と、属していない独立企業とに分類し、それぞれの設備投資関数を推計している。ここでは、トービンの平均Qと内部資金によって企業の投資を説明し、その結果、前者の企業群の方が内部資金の制約が小さくなることを明らかにしており、メインバンク関係がエージェンシーコストを軽減する機能があることを実証している。その点で、大変興味深い論文であるが、二つの大きな問題点が存在する。一つは、メインバンク関係を企業系列への所属という点から定義していることである(*6)。企業系列に属していれば必ずメインバンク関係を持ち、属していない企業はメインバンクを持たないという仮定は現実と整合的ではないと言えよう。企業系列に属していない企業であってもメインバンクを持つことは十分あり得るし、企業系列に属していてもメインバンクを持たない可能性も当然考えられる。もう一つは、ここで投資の説明変数に用いられているトービンの平均Qは、投資を説明する変数として実証的に有効ではないということである(*7)。
このような問題点を考慮した分析が、岡崎・堀内(1992)や森(1994)で行われている。これらの分析では、前者の問題に対しては、メインバンクを企業と銀行との関係によって定義することで、後者の問題に対しては、トービンのQの構成要素を平均Qの代替変数として用いることによって、解決が図られている。ここでも同様に、メインバンク関係はエージェンシーコストを削減するという結果が報告されている。これらの先行研究については、下記の表1にまとめてある。
ちなみに、どちらの分析でもメインバンク関係を定義するどの要素がエージェンシーコスト削減に対して重要なのかについても言及されており、前者ではメインバンクの融資比率が重要であり、メインバンクの継続年数もある程度の効果を持つとされている。後者では、メインバンク(最大融資行)の融資比率の変動係数(*8)が平均値よりも小さいという融資比率の安定性が重要であるとされている。
表1:先行研究の分析の比較
| 変数
|
対象業種
|
対象期間
|
メインバンクの定義 | 特徴
|
|
| Hoshi et al.
(1991)
|
設備投資額
キャッシュフロー 短期保有有価証券 平均Q 生産高 |
電気機器業種
|
1978
~1982
|
六大企業集団
に所属してい る企業
|
・メインバンクの
定義に問題あり ・平均Qが投資 の説明変数とし て不適切 |
| 岡崎・堀内(1992)
|
設備投資額
キャッシュフロー 期首資本残高 期首負債残高 資本コスト 資本の限界効率 |
電気機器業種
|
1972
~1988
|
融資比率が最大の銀行
|
・メインバンクの 機能に影響を与 える要因を分析 している
・メインバンクの 定義が一面的 |
| 森
(1994)
|
設備投資額
キャッシュフロー 期首長期借入残高 資本コスト 投資収益率
|
電気機器業種
化学業種
|
1981
~1990
|
融資比率が最大でその融資比率変動が平均よりも小さい銀行
|
・メインバンクの 定義に重要な要 因を分析してい る
・バブル期のメイ ンバンクの機能 を分析している |
この分析では、先行研究と同様に、企業の投資関数を用いて、メインバンクのエージェンシーコスト削減機能(=内部資金制約の緩和機能)について分析していく。 まず、企業の投資関数を定式化を行う。Hoshi et al.(1991)が用いているトービンの平均Qは、投資に関する全ての情報を織り込んでいると考えられるので、理論的にはこれを用いるだけでよいのだが、既に述べたように平均Qは投資の説明変数として不適当であるといわれている。そこで、この分析では、岡崎・堀内(1992)や森(1994)と同様に平均Qを構成する要素を説明変数として用いることにする。具体的には、①投資収益率と、②(狭義の)資本コストを説明変数として用いる(*9)。①の投資収益率は、企業の直面する投資の利潤率の代理変数であり、これが大きいほど利潤率の高い投資機会が存在するので、投資に対して正の影響を与えると考えられる。②の資本コストは企業が外部資金を導入する際のコストである。これが大きいほど外部資金のコストが高くなるため、投資に対して負の影響を与えると考えられる。 さらに、エージェンシーコストの影響を計測するために、③内部資金量(キャッシュフロー)と④期首負債残高を加える。既に述べたとおり、エージェンシーコストが存在するならば、外部資金の導入は内部資金に比べてその分コストが高くなる。そのため、投資は内部資金量に影響されるので、③の内部資金量は投資に対してプラスの影響を与える。④の期首負債残高については、この増加に比例してエージェンシーコストが増大すると考えられるため、投資に対してマイナスの影響を与えると考えられる。 これらに加えて、ストック調整について考慮するために⑤期首時点での固定資産残高も変数として採用する。
上記の5つの変数によって、以下のような回帰式を作成し、回帰分析を行う。なお、Iは投資、ROAは投資収益率、INTは資本コスト、CFは内部資金量、DBは期首負債残高、FAは固定資産残高である(*10)。
| ①投資収益率 | ②資本コスト | ③内部資金量 | ④負債残高 | ⑤固定資産残高 | |
| 予想される符号 | 正 | 負 | 正 | 負 | 負 |
なお、分析に用いるデータは、81年、86年、91年、96年、99年度の電気機器業種に属する上場企業の財務データである。電気機器業種を用いるのは、先行研究において用いられており、比較が可能になるためである。また、90年代以降の分析は、先行研究では行われておらず、本稿がメインバンク関係の現状について初めて明らかにするものであり、その点に大きな意義をもつものである。
4.1.分析の結果
回帰分析を行う前に、データを簡単に整理したものを見てみよう。
|
|
|
|
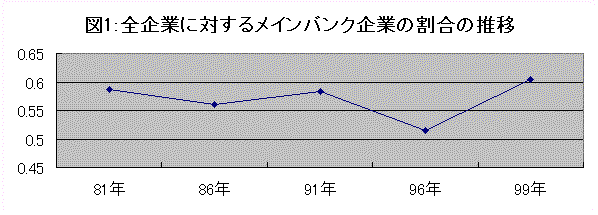
上の表3と図1は、分析に用いた企業の分析対象年度の総企業数に対するメインバンク企業の割合を示したものである。この図と表からもわかるように、メインバンク制度の崩壊などといわれてはいるものの、99年のメインバンク企業の割合は81年の割合と変わらない水準にある。このことから、メインバンクを持つ企業が減少しているわけではないことが確認できる。
では、回帰分析の結果について見ていこう。下の表4,表5は回帰分析を行った結果を示したものである。 まずは、全期間の分析から見ていこう。ここでは、負債残高は投資に対して有意な影響を与えていない。また、キャッシュフローは、メインバンク企業、独立企業ともに有意な影響を与えている。しかし、ここからは、メインバンクがエージェンシーコストを削減する機能を持っているということはできない。わずかに、CFの係数はメインバンク企業の方が小さくなっているが、その差は統計的に有意な値ではない。
表4:メインバンク企業の分析結果
|
|
定数項 | CF | DB | ROA | FA | INT | R2 | D.W. |
| 全期間 | -0.00121 | 0.01864** | -0.03482 | 0.31037** | 0.16638** | -0.42619** | 0.348 | 1.68 |
| [484] | (-0.09) | (2.78) | (-1.04) | (6.71) | (8.92) | (-2.80) | ||
| 1981年 | -0.02471 | 0.02234** | -0.05697 | 0.15581* | 0.20321** | -0.04379 | 0.216 | 1.88 |
| [81] | (-1.05) | (2.23) | (-0.80) | (1.91) | (4.14) | (-0.17) | ||
| 1986年 | 0.02798 | 0.73416** | 0.04458 | 0.21768 | 0.01997 | -0.17826 | 0.309 | 1.94 |
| [97] | (1.63) | (2.38) | (0.43) | (1.21) | (0.29) | (-0.72) | ||
| 1991年 | 0.41891** | -0.04123 | 0.12528 | -4.19344 | -0.07342 | -1.89332 | 0.508 | 2.12 |
| [106] | (3.97) | (-0.69) | (0.28) | (-10.00) | (-0.37) | (-1.13) | ||
| 1996年 | 0.00722 | 0.76161** | -0.05263 | -0.41031** | 0.09085* | -0.32365 | 0.239 | 2.13 |
| [100] | (0.42) | (3.77) | (-0.73) | (-2.03) | (2.72) | (-0.75) | ||
| 1999年 | -0.02738 | 0.02465** | -0.19296** | 0.15467 | 0.08814** | 0.66602 | 0.137 | 1.64 |
| [100] | (-1.39) | (2.02) | (-3.15) | (1.46) | (2.44) | (1.06) |
| 定数項 | CF | DB | ROA | FA | INT | R2 | D.W. | |
| 全期間 | 0.02172 | 0.01884** | -0.04508 | 0.24436** | 0.11389** | -0.1523* | 0.316 | 1.92 |
| [353] | (1.39) | (2.59) | (-0.74) | (4.47) | (5.07) | (-1.70) | ||
| 1981年 | 0.02114 | 0.02722* | -0.07538 | 0.25786** | 0.16963** | -0.29387 | 0.186 | 1.80 |
| [57] | (0.54) | (1.80) | (-0.64) | (2.61) | (-1.29) | (-1.29) | ||
| 1986年 | -0.00081 | 0.56609** | 0.4858** | 0.00551 | 0.13476* | -0.02845 | 0.298 | 1.77 |
| [53] | (-0.03) | (2.08) | (2.88) | (0.02) | (3.33) | (-0.21) | ||
| 1991年 | -0.01847 | -0.00831 | -0.53964 | 0.05704 | 0.3375** | 0.82519 | 0.093 | 1.84 |
| [75] | (-0.32) | (-0.39) | (-1.16) | (0.15) | (2.87) | (1.07) | ||
| 1996年 | 0.03792** | 0.93981** | -0.02864 | -0.57135** | -0.04508 | -0.23394 | 0.250 | 1.92 |
| [92] | (2.66) | (5.35) | (-0.37) | (-3.70) | (-1.30) | (-1.15) | ||
| 1999年 | -0.05537** | 0.03104** | 0.02996 | 0.51908** | 0.16869** | -0.29042** | 0.268 | 2.00 |
| [76] | (-2.56) | (2.66) | (0.14) | (3.08) | (4.75) | (-2.02) |
次に、81年度の分析を見てみよう。ここでも、全期間の場合と同様に負債残高は有意ではない。しかし、キャッシュフローについては、大きな差があり、メインバンクを持つ企業の方が、より緩やかな内部資金制約の中にいることがわかる。つまり、メインバンク関係が理論通りの機能を発揮していると考えられる。しかし、メインバンク企業のCFの係数も有意に0とは異なっており、内部資金制約から完全に解放されているわけではない。
次に、86年度と91年度の分析を見てみよう。86年については、負債残高については有意ではなく、内部資金制約も緩和されていない。それどころか、有意ではないとはいえ、メインバンク企業の方が厳しい内部資金制約の元におかれているという結果がでている。91年度の方は、全く有意な結果がでていない上に、符号も予想と異なり、バラバラになっている。
96年の分析においても、負債残高の係数は有意になっていない。しかし、内部資金制約緩和機能はしっかりと計測されている。また、メインバンク企業、独立企業ともにROAの符号が予想と異なっている。
最後に、99年度の分析を見てみよう。99年度の分析は、唯一負債残高の係数が有意に計測されており、内部資金制約緩和機能も有意に計測されている。
また、91年のメインバンク企業、96年の独立企業を除いて、固定資産残高の符号が理論と異なっている。
4.2.結果の考察
それでは、上記の結果について考察していこう。まず、91年について、全く有意な結果が得られなかった理由から考えてみよう。91年といえば、バブルの末期であり、地価がピークに達していた時期である。そのことから考えると、この時期には土地資産の含み益の増大などを背景にして、短期的には低コストで、エクイティファイナンスによる資金調達が容易に行えたために、企業は内部資金制約から解放されていたという見方ができる。また、この時期には銀行借入も容易に行えたため、メインバンク関係を持たない企業も持つ企業も、ほとんど制約を受けずに借入が行えたという見方もできるだろう。森(1994)も、バブル期のサンプルを分析し、金融緩和期には、メインバンクが果たすのと同じような効果が観測されたと述べており、この結果はこのことと整合的な結果であると言えよう。このような見方が正しいとすれば、91年の値は特殊な値であるので、その分析について考察する必要はないと言えるだろう。
では、残りの4年分の分析から、何が言えるだろうか。まず、負債残高は、唯一99年度のメインバンク企業の分析でのみ有意に観測されたが、その他の分析では全て有意ではない。このことから、負債残高は投資にそれほど影響を与えないということが言えるであろう。つまり、負債残高が増加するとエージェンシーコストを大きくなると考えられるが、その度合いは大変小さいものだろうということである。また、唯一99年のメインバンク企業のみ有意に観測されたのは、銀行がリスクに対して敏感になり、借入金残高の多い企業に対する融資に慎重になったためと考えることができるだろう。銀行に、より強く依存するメインバンク企業では係数が有意に観測され、独立企業では観測されなかったことも同様に説明できる。 また、固定資産残高(FA)の係数はほぼ全ての年において、予想された符号と異なった。これは、この変数が個別企業の業態の違いを表していたためと考えられる。つまり、固定資産残高が大きい企業は多大な設備を必要とする企業であり、小さい企業はそれほど設備を必要としない企業であるため、資産残高の大きい企業ほど投資が多くなったということである。この効果が、ストック調整の効果を上回ったためにこのような結果になったのだろう。
次に、内部資金制約については、全ての年度において有意に観測された。また、内部資金制約の緩和についても、86年度を除く3年の分析からは観測された。このことから、やや説得力に欠ける部分もあるが、メインバンク関係には、内部資金の制約を緩和するという機能が確認されたと言えるだろう。
では、内部資金制約の緩和機能は、年代とともにどう変化したのだろうか。上の図2は、メインバンク企業と独立企業のキャッシュフローの係数の差と比率をグラフにしたものである。このグラフを見ると、81年度の機能の水準に比べて、96年度、99年度の水準は低くなっている。しかし、96年度、99年度ともに、内部資金制約の緩和機能は発揮しており、その機能は安定しているように見える。観測した値が少ないために正確なことは言えないが、81年の水準がそれ以前の平均的な機能水準であるとすれば、確かに、バブル崩壊後のメインバンク関係は、以前ほどの機能を発揮することができていないことになる。また、メインバンク関係がエージェンシーコストを削減し、外部資金のコストを引き下げることによって、外部資金の利用可能性を高めるのであれば、メインバンクを持つ企業は持たない企業よりも多くの投資を行えるであろうと考えられる。
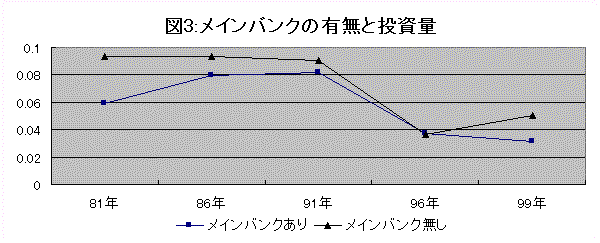
しかし、メインバンク企業と、独立企業の投資量を比較してみると、図3のように、全ての年度において独立企業がメインバンク企業を上回っている。この理由としては、メインバンク関係の他の機能(保険提供機能等)のコストをメインバンク企業が負担しているため、メインバンクからの借入が単純に独立企業のそれと比べて、コストの低いものではない可能性があるということがあげられる。さらに、独立企業の中には低コストで資本市場からの資金調達が可能な(また、そのためにメインバンクを持つ必要がない)超一流企業が含まれているため、メインバンク企業のコストが高くなっていると考えることもできる。しかし、このように独立企業よりも投資量が少ないということは、メインバンクのもつ投資資金の柔軟な供給という機能がそれほど大きな働きをするものではないことを示唆していると考えることも可能だろう。
ここまでのことをまとめると、以下のようになるだろう。メインバンク制度の崩壊といったことが叫ばれているが、メインバンク関係を持っている企業の割合にそれほど変化はない。しかし、その一方でメインバンクの機能は以前に比べて低下している可能性がある。また、メインバンクの機能も、それほど高い機能を発揮していたわけではないと考えられる。岡崎・堀内(1992)においても同様の見方がなされており(*13)、この結果はそれと整合的であると言える。
4.3.今後のメインバンク関係
ではメインバンク関係は今後どうなっていくのだろうか。メインバンクの機能の水準が落ちていること、メインバンクの機能がそれほど大きくない可能性があることを示してきたが、もう一つの見方が可能である。下の図4は、全企業の投資量を表したグラフである。
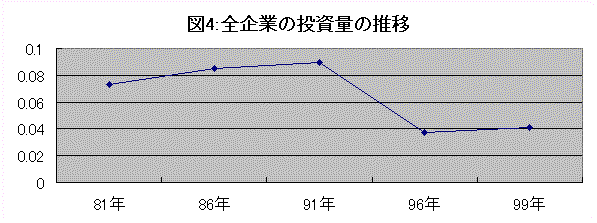
このグラフを見ると、96年、99年はそれ以前と比べて、明らかに投資量の水準が低くなっていることがわかる。この、投資量の水準の低さがメインバンクの機能水準を低くしているという可能性も考えられるのである。事実、大庭・堀内(1990)はHodderの議論を引用し、メインバンクを持つ企業と持たない企業の有利性について、financing hierarchy理論を用いて説明しているが、その結論は、投資機会が豊富な企業はメインバンクを持つことで資本コストを引き下げることができるというものである(*14)。この考え方にのっとれば、今後日本経済がアメリカのように高い経済成長を実現することがあるのならば、メインバンク関係は有益なシステムとして機能するであろう。そのような状況が生まれなくとも、高成長を続けている業種に属す企業などは、メインバンク関係を持つことによって、より多くの投資を行い、利益を得ることができる。また、中小企業のように、銀行借入以外の資金調達の道が閉ざされている企業にとっても、メインバンク関係は有益なものとして機能し続けるだろう。
メインバンク関係は、投資に対する内部資金制約を緩和するのかどうか検討し、その機能は近年衰えてきているのかについても検討してきた。結果としては、①メインバンク関係には、エージェンシーコストの削減を通じた内部資金制約緩和機能があること、②バブル期以降、メインバンクの機能が低下していること、が結論としてあげられる。 実証分析については、標本データの連続性がないなどの問題や、決定係数が低く投資関数の定式化にも問題があった可能性が大きいが、上記の結論を支持するものであったといえるだろう。また、今回は、たった5年分のデータからの分析であったため、正確性に欠ける部分、説得力に欠ける部分等があった。とはいえ、今回の結果は、メインバンクの機能低下の可能性を示せたという点で、意義があったと考える。
本稿では、近年非難を浴びることが多い日本型システムの中でも代表的なメインバンク関係の機能について焦点を当ててきた。このことについては、一応の結論がでたが、いくつかの問題意識が残った。一つは、これからのメインバンク制度はどうなるかについて述べた部分で、中小企業にとっては、有意義なものであり続けるだろうと、書いた。しかし、このことについても、中小企業におけるメインバンクの機能は果たして大企業におけるそれと比べてどうなのかといった点について、今後の分析が必要になるだろう。また、成長率の全く異なる業種間では、メインバンクの機能に変化があるのかどうかといったことについても、分析が必要だろう。
[10]同『企業系列総覧1992』.[11]同『企業系列総覧1987』.
[12]同『企業系列総覧1982』.
[13]同『企業系列総覧2000』.
[14]日経NEEDS 財務データ.
上記の分析において用いたデータについてふれておく。全てのデータは、日経NEEDSより入手した財務データを元にしている。また、全てのデータは2年間の平均値を用いており、年の区分は、80年4月から81年3月までの決算期を81年のデータとして扱っている。つまり、81年のデータは、80年4月から81年3月までの決算のデータと、その一期前の決算との平均値によって作成されている。
決算期が変更され、12ヶ月に満たない場合には、その一期前の値までさかのぼり、そこから計算された値を12ヶ月換算した。
合併や分割等により、データの連続性が失われていると考えられる企業については、標本から除いている。 最後に、全ての変数の計算方法と回帰式を以下に記しておく。
①投資収益率(ROA)
投資収益率には総資産収益率を用いた。
(総資産収益率)=(税引き前利益)÷(資産合計)
②資本コスト(INT)
(資本コスト)=(支払利子)÷(有利子負債)
③内部資金量(CF)
内部資金量にはキャッシュフローを用いた。
(キャッシュフロー)=(当期利益)+(減価償却費)-(株主配当金)-(役員賞与)
④期首負債残高(DB)
期首負債残高には長期借入金残高を用いた。
⑤期首固定資産残高(FA)
期首固定資産残高には固定資産残高を用いた。
⑥投資額(I)
(投資額)=(期末固定資産残高)-(期首固定資産残高)+(減価償却費)